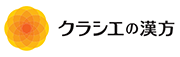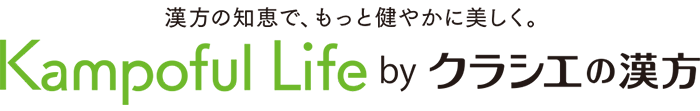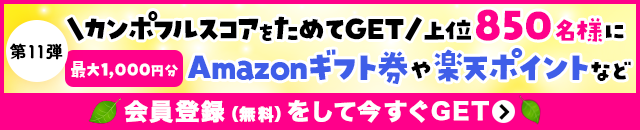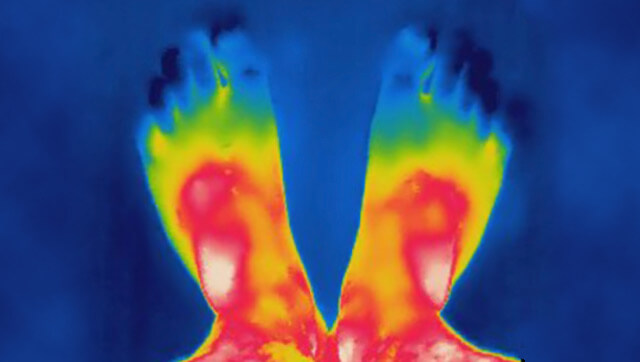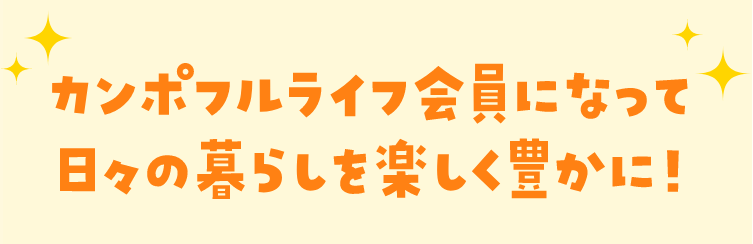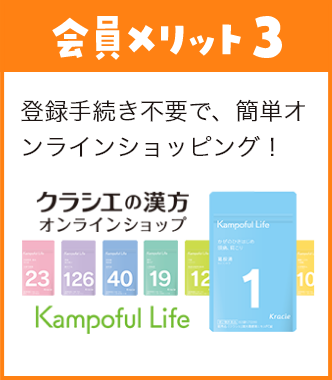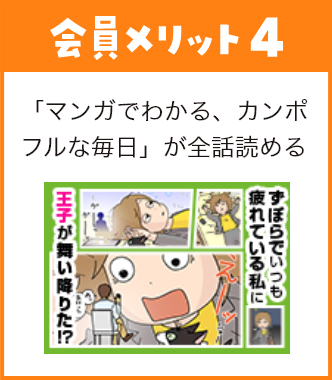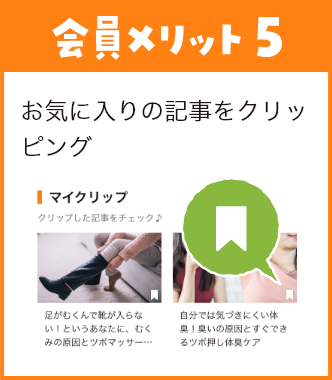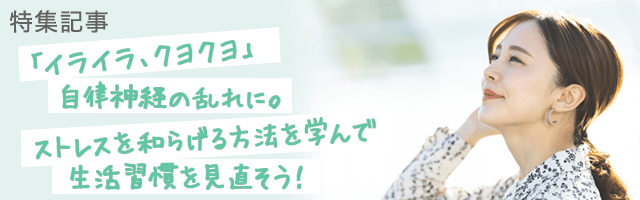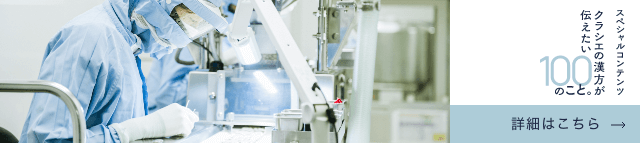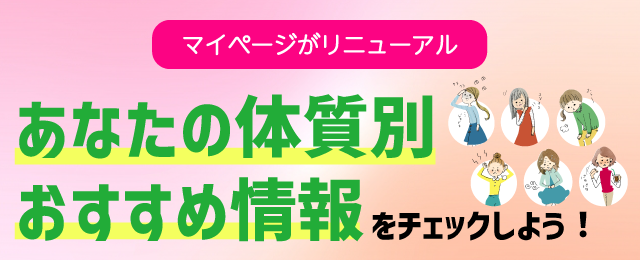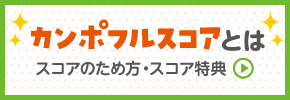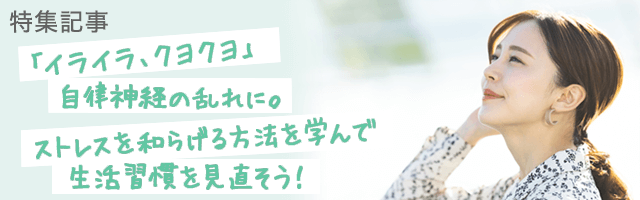目次
- あなたの「耳鳴り」タイプは?耳鳴り4つの原因
- 「耳鳴り」を和らげてくれる漢方薬
- 「耳鳴り」をセルフケアで改善しましょう
- 受診勧奨の耳鳴り
- 急に耳鳴りが起こる原因は?
- 耳鳴りはどんな病気の兆候ですか?
- 耳鳴りの音の高さの違いとは?
耳鳴りは自分にしか聞こえない音に悩まされるトラブル。そのため、自分では耳鳴りだと気づきにくかったり、人に伝えにくかったりしがちです。また、症状を引き起こしている原因によって対処の仕方も異なるものです。そこで今回は、漢方の視点から見た耳鳴りの改善法について解説します。
あなたの「耳鳴り」タイプは?耳鳴り4つの原因
耳鳴りと聞くと「キーン」などと耳に響く高音を想像しがちですが、実際はゴゴゴゴという低く詰まった音や、虫が鳴くような音、すき間風が吹くような音まで、さまざまな種類があります。甲高い金属音などすぐに自覚できる音とは限らないので、注意しましょう。
漢方では耳鳴りの聞こえ方や体調などによって、主に4つの原因があると考えます。
①ストレスが原因のタイプ
□金属音や電子音のような高い音を感じる
□大きな音が鳴り響くこともある
□耳鳴りだけでなく肩も凝っている
□生活が不規則になりがち
□普段からイライラしやすい
ココロとカラダに負担がかかっている可能性があります。慢性的なストレスを溜めていませんか。もし耳鳴りがひどい場合は病院に行くことをおすすめします。と同時に、仕事や家事で無理をしすぎない、意識的に休む時間を作るなど、生活習慣の見直しが必要です。アロマの香りや温かいお茶を取り入れるのも良いでしょう。
②加齢や老化が原因のタイプ
□虫が鳴いているような音を感じる
□カラダに力が入りづらい
□高血圧の傾向がある
□耳が聞こえづらい
□尿トラブルや物忘れもある
成長や発育、生殖機能を司る「腎(じん)」が衰えている可能性があります。加齢や老化によって、腎の働きは弱まりがちに。腎のエネルギーが不足しないように、なにごとも頑張りすぎない過ごし方を心がけましょう。また、黒色の食材は腎の働きを助けます。黒ゴマや黒米、黒豆などの食材を食生活に取り入れるのもおすすめです。
③水の巡りの滞りが原因のタイプ
□テレビの砂嵐(ホワイトノイズ)のようなザーザー音がする
□頭がぼーっと、重だるくなる
□めまいやふらつきがある
□足がむくみやすい
□手足が冷えやすい
水分代謝が悪くなっているため、手足のむくみも気になるかもしれません。胃腸への負担も考えられます。お風呂に入らずにシャワーで済ませたり、甘いものばかり食べていたりしていませんか。冷たい飲み物を控える、消化に良い食材を食べるなど、冷えを防いで代謝を促すライフスタイルを意識してみてください。
④風邪や発熱などが原因のタイプ
□熱が出てから耳鳴りがする
□耳が痛くてつらい
□急に耳鳴りが気になるようになった
□普段は耳鳴りに悩んでいない
□関節痛や頭痛も感じる
慢性的な耳鳴りではなく、風邪や発熱などが影響している「急性」の不調である可能性が考えられます。ウイルス性の症状とともに、突然耳鳴りを感じるようになった方がこのタイプ。耳の痛みや詰まっている感覚もあるでしょう。まずは休んで体調を回復させることが第一。慢性的な耳鳴りにならないように、しっかりと治すことに専念しましょう。
「耳鳴り」を和らげてくれる漢方薬
加齢とともに衰えがちな耳の働きを補ってくれる漢方薬といえば、七物降下湯(しちもつこうかとう)です。七物降下湯は、血圧の上昇やのぼせを本来の状態に整えながら、慢性的な耳鳴りを緩和する働きがあります。
■七物降下湯(しちもつこうかとう)
七物降下湯は古くからカラダの栄養である血を補う基本処方とされてきた四物湯(しもつとう)に3種類の生薬を加えた漢方薬です。元々高血圧の随伴症状の改善を目的に作られた処方で、高血圧に伴うのぼせや肩こり、耳鳴りや頭重などに効果を発揮します。血をしっかりと補うと同時に、気を補い、気血を充実させるとともに、余分な熱を冷まします。
<PR>
「耳鳴り」をセルフケアで改善しましょう
<セルフケアの方法>
・ストレスを管理する
ストレスは耳鳴りを悪化させることがあります。リラクゼーション法や瞑想、深呼吸などを試してみてください。
・騒音を避ける
大きな音や長時間の騒音を避けて、耳の負担を減らしてあげましょう。
・耳栓やホワイトノイズを利用する
耳栓の使用や、ホワイトノイズを流すことで耳鳴りを軽減することができます。
・健康的な生活習慣を心がける
規則正しい生活、バランスの取れた食事、適度な運動、良質な睡眠が耳鳴りの改善に役立ちます。
・カフェインやアルコールを制限する
これらは耳鳴りを悪化させることがあるため、控えることをおすすめします。
近年、耳鳴りに悩む方は若い世代にまで増えています。夜遅くまでスマートフォンやパソコンに触れて睡眠不足になっていませんか。ヘッドフォンで音楽を大きな音で聴いていませんか。
耳鳴りを改善するには、まず十分な睡眠をとることが大切です。寝る前は頭や目がリラックスできる環境で過ごし、良質な眠りによって元気なカラダを作る元となる「気(き)」を補充しましょう。
そして、言うまでもなく ココロとカラダは良質な食べ物から作られます。新鮮な旬の食材をシンプルな味付けで調理して召し上がってみてください。特別なメニューを作る必要はありません。
食生活やライフスタイルを整えることで、耳鳴りや手足の冷え、むくみが緩和されることがあります。
受診勧奨の耳鳴り
耳鳴りはさまざまな原因で起こるため、適切な診断と治療が重要です。セルフメディケーションで改善しない場合や不安がある場合には、早めに耳鼻科の受診をおすすめします。では、受診を検討すべき耳鳴りをパターン別に見てみましょう。
「耳鳴りが突然始まった」
突然の耳鳴りは、耳や脳の問題を示している可能性があるため、早めに受診しましょう。
「耳鳴りが続いている」
数週間以上続く耳鳴りは、専門的な評価を受ける必要があります。
「日常生活に支障をきたす」
仕事や睡眠に影響を与えるほどの耳鳴りは、診察を受けるべき状態です。
「めまいや難聴、耳の痛みなどがある」
めまいや難聴、耳の痛みなどがある場合、すぐに受診してください。
急に耳鳴りが起こる原因は?
耳が急に「キーン」「ピー」となる原因は、多岐にわたります。考えられる原因を見てみましょう。
まず、突発性難聴が考えられます。突発性難聴は急に聞こえが悪くなるもので、ストレスや疲労、睡眠不足が引き金になることがあります。
次に、メニエール病が挙げられます。これは内耳のリンパ液が異常に増加することで起こり、めまいや耳の閉塞感を伴います。
加齢も一因です。聴神経の衰えで難聴や耳鳴りが発生することがあります。
また、中耳炎や中耳の腫瘍も原因として考えられます。耳炎や中耳炎は感染や炎症が原因で、聴神経腫瘍は良性ですが聴力に影響します。
さらに、筋肉の緊張や痙攣も耳鳴りの原因となることがあります。
外部環境が原因となることもあります。
気圧の変化も耳に影響を与え、特に飛行機内や高地で感じやすいです。騒音や大音量の音楽も耳に負担をかけ、聴神経にダメージを与える可能性があります。
耳鳴りはさまざまな病気と関連していることがあり、ほとんどのケースでは一時的なものですが、症状が続く場合は専門医の診察を受ける必要があります。
耳鳴りはどんな病気の兆候ですか?
耳鳴りは多くのケースでは一時的なものですが、人によっては重篤な病気の兆候である場合もあるため注意が必要です。
耳鳴りの主な原因は前章で見た通りで、聞こえ方の異常やストレス、脳の異常、中耳炎、中耳や外耳の問題、血圧の変動、老化などが挙げられます。メニエール病や聴神経腫瘍、脳梗塞などの重篤な疾患の場合も考えられます。これらの病気は脳や中耳、外耳、血液の循環に関連しています。
他にも、血圧の上昇やストレスなどが引き金となる場合があります。中耳炎や耳炎は感染症が原因であり、聴神経や中耳、中耳炎に関連する疾患が耳鳴りを引き起こします。聴神経腫瘍は良性の腫瘍ですが、聴力に影響を与え、耳鳴りを発生させることがあります。
耳鳴りの音の高さの違いとは?
耳鳴りの「ボー」と「キーン」「ピー」の違いは、音の高さにあります。
「キーン」「ピー」のような高音の耳鳴り
内耳や聴神経に関連する問題の場合が多く、突発性難聴やメニエール病などの病気が原因となっている可能性があります。高音の耳鳴りは、内耳の液体の異常や神経の異常によって引き起こされ、めまいや難聴を伴う場合があります。
「ボー」という低音の耳鳴り
低温の耳鳴りは、中耳や外耳の問題に関連していることが多く、中耳炎や耳管の機能不全、外耳の炎症が原因となる場合があります。ストレスや気圧の変化によって引き起こされることもあります。
耳鳴りの症状が続く場合は、専門医の診察を受けることが重要です。
<PR>