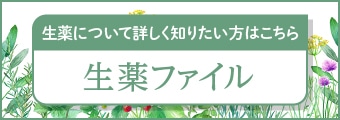一般的に「むくみ」に使われる漢方薬
【漢方薬名解説】
防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)
公開日:2018年08月01日最終更新日:2025年06月20日
目次
肥満や汗っかきで疲れやすい方向けの漢方薬「防已黄耆湯」
漢方では、飲食物から「気」「血(けつ)」がつくられ、体のすみずみに運ばれて体を動かしていると考えます。一般に胃腸が弱い方では、飲食の過剰はなくても、体が処理しきれずに余るため肥満となります。そこで、「気」を補い、胃腸のはたらきを高めるとともに、余分な「水(すい)」の排出を促します。「防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)」は、消化吸収を助けながら、余分な「水(すい)」をとり除き、全身の機能を高める作用のある医薬品です。胃腸がきちんと機能することによって、体に必要なエネルギーをつくり出し、消費することができるようになります。また、余分な「水(すい)」を排泄することで、体をひきしめ、水太りやむくみ(浮腫)を改善することができるお薬です。
また、「防已黄耆湯」は一般的に多汗の方にも有効な医薬品です。多汗になる原因も肥満と同様で、体の水分バランスが乱れるために、体が発汗異常を起こしてしまう状態なのです。そのため、体の水分バランスを整えることで汗が抑えられます。また、ひざの痛みや関節の痛みの元も、体の水分バランスの乱れによるもの。このタイプの方は、もともと水分を体に溜め込みやすい体質なので、日頃から冷たいものを食べ過ぎたり、水分を摂り過ぎたりしないように注意して、水太りや関節のケアを意識しましょう。
効能・効果
体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症:肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)
配合生薬(成分・分量)
成人1日の服用量12錠(1錠351mg)中
防已黄耆湯エキス…3200mg
(ボウイ・オウギ各5.0g、ビャクジュツ・タイソウ各3.0g、カンゾウ1.5g、ショウキョウ1.0gより抽出。)
添加物として、タルク、ステアリン酸Mg、二酸化ケイ素、CMC-Ca、クロスCMC-Na、水酸化Al/Mg、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、ヒプロメロースを含有する。
成分に関連する注意
本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。
用法・用量
次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。
| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|---|---|---|
| 成人(15才以上) | 4錠 | 3回 |
| 15才未満5才以上 | 2錠 | |
| 5才未満 | 服用しないこと | |
用法・用量に関連する注意
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
注意点・副作用
使用上の注意
- 相談すること
- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)高齢者
(4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
(5)次の症状のある人
むくみ
(6)次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病 - 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
皮膚 発疹・発赤、かゆみ 消化器 食欲不振、胃部不快感
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。間質性肺炎 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 偽アルドステロン症、ミオパチー 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 肝機能障害 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 - 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
保管方法
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4)ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますのですててください。
(5)使用期限のすぎた商品は、服用しないでください。
(6)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。
製品情報
むくみがあり、太り気味の方に
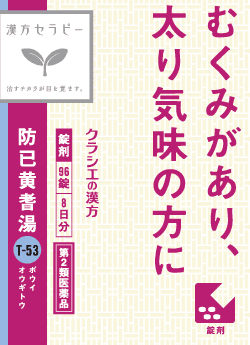
防已黄耆湯エキス錠Fクラシエ
第2類医薬品
防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)
体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症:肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)
一般的に「むくみ」に使われる漢方薬