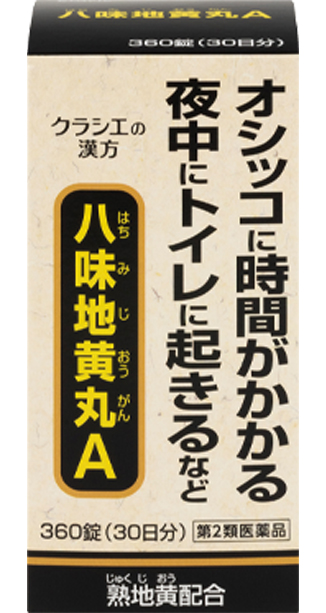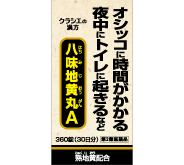
八味地黄丸とは?
効果/作用機序
1
八味地黄丸とは

八味地黄丸は、「腎虚(じんきょ)」の症状に対して用いられる代表的な処方で、「温補腎陽(おんぽじんよう)」という考え方のもと作られています。 「腎虚」とは泌尿器・生殖器・腎臓などを指す「腎(じん)」の機能が低下している状態をいいます。詳しくは 「腎虚について」をご覧ください。 「温補腎陽」とは、エネルギーをつくり出す力を高めてからだを温めるとともに、「腎陽」を補うことを意味します。
「腎陽」とは身体を温めたり機能させたりするエネルギーの大元のこと。つまり八味地黄丸は、全身を温めて泌尿器や生殖器・腎臓の機能を高め、機能低下によって生じるさまざまなトラブルを改善する漢方です。からだを温める生薬をメインに8種類の生薬で構成され、腎陽虚の人に起こりがちな、さまざまな症状に効果的です。
2
八味地黄丸を
おすすめしたい方の
特徴
疲れやすい
四肢が冷えやすい
尿の量が多かったり
少なかったりする
口が渇く傾向にある
八味地黄丸は、こうした悩みをお持ちの方におすすめです。また、こうした症状をお持ちの方は舌の色が白っぽいことがあるので確認してみましょう。
3
八味地黄丸の
効能・効果
上述したように、八味地黄丸には「腎」機能の低下を改善するはたらきがあります。そのため
排尿困難や残尿感、夜間尿、頻尿や軽い尿漏れなどの尿トラブルに効果があります。
また、中医学ではかすみ目や老眼などの目の症状は、視覚系の機能を司る「肝」のはたらきが弱ったり、「肝」を助ける「腎」や「肝」を打ち消す「肺」とのバランスが崩れることによって生じると考えられています。

そのため、
「腎」の機能を整える八味地黄丸はかすみ目などの症状にも効果的です。他にもしびれやむくみやかゆみ、下肢や腰の痛み、高血圧に伴う肩こりや頭重、耳鳴りにも有効です。
具体的な効能・効果については
「八味地黄丸の商品解説」、症状別の解説は「腎虚について」内のそれぞれの症状ページをご覧ください。
また、「女性の尿トラブル」 「男性の尿トラブル」でも詳しく解説しています。
4
八味地黄丸の
配合生薬
八味地黄丸は 桂皮、地黄、 山茱萸、山薬、附子、牡丹皮、沢瀉、茯苓の8つの生薬からできています。これらの生薬は腎の働きをよくしてくれるため、「腎」機能の低下状態に効果的です。 ここでは各生薬について解説します。なお、生薬の基原植物は多数存在する場合があります。その場合は多くの基原植物の中の一つをご紹介します。

桂皮(ケイヒ)
桂皮とは、クスノキ科桂の樹皮や周皮の一部を除いたものを基原とする生薬です。

地黄(ジオウ)
地黄とは、ゴマノハグサ科アカヤジオウの根を基原とする生薬です。

山茱萸(サンシュユ)
山茱萸とは、ミズキ科サンシュユの偽果の果肉を基原とする生薬です。

山薬(サンヤク)
山薬とは、ヤマノイモ科ヤマノイモまたはナガイモの周皮を除いた根茎を基原とする生薬です。

附子(ブシ)
附子とは、キンポウゲ科ハナトリカブト、オクトリカブトの塊根を基原とする生薬です。

牡丹皮(ボタンピ)
牡丹皮とは、ボタン科ボタンの根皮を基原とする生薬です。

沢瀉(タクシャ)
沢瀉とは、オモダカ科サジオモダカの塊茎、通例、周皮を除いたものを基原とする生薬です。

茯苓(ブクリョウ)
茯苓とは、サルノコシカケ科マツホドの菌核を基原とする生薬です。
5
八味地黄丸の
用法・用量
用法・用量は商品によって異なります。
1回に服用する量や1日の服用回数、服用可能な年齢などは商品の「用法・用量」を読み、正しくお使いください。
「八味地黄丸A」の用法・用量は
「八味地黄丸の商品解説」をご覧ください。
6
八味地黄丸を
服用する際の注意点
胃腸の弱い人や下痢しやすい人は服用をお控えください。また、以下に該当する方は服用する前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
●医師の治療を受けている人
●妊婦または妊娠していると思われる人
●のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
●今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
発疹、発赤、かゆみ、食欲不振、胃の不快感、腹痛、動悸、のぼせ、口唇や舌のしびれなどの症状が生じた場合は副作用の可能性があります。服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。また、1カ月ほど服用しても症状がよくならない場合も服用を中止して医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
その他、保管方法などの注意点は
「八味地黄丸の商品解説」にて詳しく解説しています。併せてご覧ください。
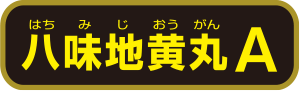 のご購入について
のご購入について
■価格
| 容量 | 希望小売価格(税込) |
|---|---|
| 60錠(5日分) | 1,089円 |
| 180錠(15日分) | 2,662円 |
| 360錠(30日分) | 4,598円 |
| 540錠(45日分) | 6,017円 |
■効能
体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渇があるものの次の諸症:下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ
■成分
成人1日の服用量12錠(1錠305mg)中、次の成分を含んでいます。
ジオウ(熟ジオウ)末・・・890mg
サンシュユ末・・・445mg
サンヤク末・・・445mg
タクシャ末・・・334mg
ブクリョウ末・・・334mg
ボタンピ末・・・334mg
ケイヒ末・・・111mg
ブシ末・・・111mg
添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、ハチミツ、ポビドン、ステアリン酸Mg、ケイ酸Al、白糖を含有する
成分に関連する注意
本剤は天然物(生薬)を用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。
■用法・用量
次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。
| 年齢 | 1回量 | 1日
服用回数 |
| 成人
(15才以上) |
4錠 | 3回 |
| 15才未満 | 服用しないこと | |
■使用上の注意
●してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は服用しないでください
(1)胃腸の弱い人
(2)下痢しやすい人
●相談すること
1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
(4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感、
腹痛 |
| その他 | 動悸、のぼせ、
口唇・舌のしびれ |
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
4. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
■保管及び取り扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(ビン包装の場合は、密栓して保管してください。なお、ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますのですててください。)
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4)ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますのですててください。
(5)使用期限のすぎた商品は、服用しないでください。
(6)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。